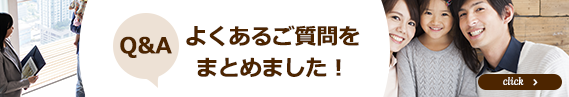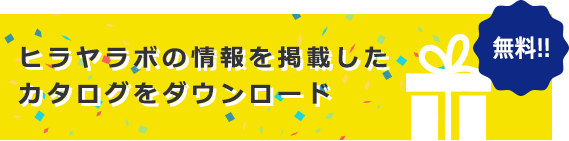快適な住まいづくりのためのQ値・UA値とは?
2025.03.10
快適な住まいづくりには、断熱性能が欠かせません。
新築住宅を検討する際に、よく耳にする「Q値」と「UA値」。
これらの数値が、どのような意味を持ち、どのように計算され、どのような基準があるのか、戸惑っている方もいるのではないでしょうか。
今回は、Q値とUA値について、分かりやすく解説します。
Q値とUA値とは何か?断熱性能を理解する
Q値の定義と意味
Q値は「熱損失係数」と呼ばれ、住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを表す数値です。
数値が小さいほど、熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。
延べ床面積を元に計算するため、建物の大きさの影響を受けやすい点が特徴です。
換気による熱損失も考慮されます。
UA値の定義と意味
UA値は「外皮平均熱貫流率」と呼ばれ、Q値と同様に断熱性能を表す数値です。
住宅内部の熱が、屋根、外壁、床、窓などの外皮を伝わって外部に逃げる速さを示します。
数値が小さいほど、熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。
Q値と異なり、換気による熱損失は考慮されません。
2013年の省エネルギー基準改正以降、Q値に代わって主要な指標として用いられています。
Q値とUA値の違い
Q値とUA値はどちらも断熱性能を表す数値ですが、計算方法や考慮する要素に違いがあります。
Q値は延べ床面積、UA値は外皮面積を基準に計算されます。
また、Q値は換気による熱損失を含みますが、UA値は含みません。
そのため、同じ断熱性能であっても、Q値とUA値は異なる数値になることがあります。
現在では、UA値の方が断熱性能をより正確に評価できる指標として広く利用されています。
Q値とUA値の計算方法
Q値の計算式は「Q値(W/平方メートル・K)=熱損失量(W/K)÷延べ床面積(平方メートル)」です。
熱損失量は、建物各部の熱損失と換気による熱損失の合計になります。
UA値の計算式は「UA値(W/m平方メートル・K)=建物各部の熱損失量(W/K)÷延べ外皮面積(平方メートル)」です。
建物各部の熱損失量は、屋根、天井、外壁、床、開口部などの熱損失量の合計です。
使用する部材の熱伝導率や、断熱方法によって熱損失量は大きく変化します。

Q値・UA値と省エネ基準の関係性
省エネルギー基準とUA値
2013年の省エネルギー基準改正以降、新築住宅の断熱性能評価にはUA値が用いられています。
省エネルギー基準では、地域区分ごとにUA値の基準値が定められており、この基準値を満たすことが求められます。
ZEHやHEAT20基準とUA値
ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)やHEAT20は、より高い省エネルギー性能を目指す住宅基準です。
ZEHやHEAT20基準でもUA値が重要な指標となっており、より厳しい基準値が設定されています。
HEAT20は地域区分ごとに複数のグレードを設定し、UA値によってグレードが評価されます。
Q値と現在の省エネ基準の関係
現在の省エネルギー基準では、UA値が主要な指標として用いられており、Q値はあまり使用されなくなっています。
ただし、一部のハウスメーカーでは、Q値も併せて提示している場合があります。
地域によるUA値基準の違い
日本の地域によって気候条件が異なるため、省エネルギー基準におけるUA値の基準値も地域によって異なります。
一般的に、寒冷地ほど低いUA値が求められます。
快適な住まいを実現するためのQ値UA値の目標値
快適な住まいを実現するためには、地域区分に応じた省エネルギー基準を満たすことはもちろん、ZEHやHEAT20基準を目標にすることも検討できます。
より高い断熱性能を求める場合は、基準値よりも低いUA値を目指すと良いでしょう。
ただし、UA値を下げるためにはコストも増加するため、予算とのバランスも考慮する必要があります。
まとめ
今回は、住宅の断熱性能を表すQ値とUA値について解説しました。
Q値は延べ床面積、UA値は外皮面積を基準に計算され、数値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。
現在の省エネルギー基準ではUA値が主要な指標となっており、地域区分ごとに基準値が定められています。
ZEHやHEAT20基準では、さらに高い断熱性能が求められます。
新築住宅を検討する際には、これらの数値を理解し、快適で省エネルギーな住まいを実現するための目標値を設定することが重要です。
地域や予算を考慮し、最適な断熱性能を検討しましょう。
当社は、お客様のご希望やご不安に寄り添い、最適な平屋のプランをご提供します。
平屋に少しでも興味のある方は、お気軽にご連絡ください。